
こんにちは、
りんとちゃーです。
花札9月札に描かれた「菊(きく)」と「盃(さかずき)」。

(左から順に「菊に盃」「菊に青短」「菊のカス」「菊のカス」)
絵柄のモチーフとなったのは、五節句の一つである「重陽(ちょうよう)の節句」の「菊酒(きくざけ)」の風習で、「重陽の節句」は、現代人にあまり馴染みがありませんが、旧暦の頃には年中行事として盛んに行われていました。
また、秋を代表する「菊」の花は、古くから格式が高い・高貴な植物と考えられていて、現在の「天皇家の紋章」にも使われています。
記事では、以下のことをまとめています。
■「菊(きく)」の特徴や語源・花言葉など
■天皇家の「菊花紋章(十六八重表菊)」について
■「重陽(ちょうよう)の節句」の由来と行事
菊について詳しく学んで、格調高きその花の恩恵にあずかりましょう。
菊(きく)

■基本データ
分類:キク科キク属
学名:Chrysanthemum
英名:Mum
和名:菊、きく
別名:齢草(よわいぐさ)
原産地:中国
花の色:白、黄色、ピンク、赤など
開花時期:9~11月
花言葉:高貴、わずかな愛、誠実
特徴・種類
中国を原産とするキク科キク属の「菊(きく)」は、密集した形の花びらが特徴で、黄色や白、ピンク、赤など、さまざまな色の花を秋頃(9~11月)に咲かせます。
「菊」が中国から日本に伝わったのは奈良時代の頃で、その後、日本だけでなく世界中で品種改良が行われていきました。
江戸時代に日本で品種改良された菊は「和菊(古典菊)」と呼ばれていて、「和菊」には「江戸菊」「嵯峨(さが)菊」「美濃(みの)菊」などの種類があります。
これに対し、イギリスを中心とする欧米で品種改良された菊は「洋菊」と呼ばれていて、種類としてはスプレーマム、ピンポンマムなどがあります。
由来・語源
漢字の「菊」は、中心に向かって巻き込む花の形を手のひらで米を握る様子に見立てたもので、学名の「Chrysanthemum」は、ギリシャ語の「chrysas」(=黄金)と「anthemon」(=花)に由来があります。
和名の「きく」の語源となったのは、以下の2説です。
①日本に伝来した時の呼び名「クク」が「キク」に変化した説。
②一年の最後に咲く花なので、日本語の「行き詰まり」と同じ意味の「極(きわ)まる」がもとになった説。
食用菊

「食用菊」とは、食べやすいように苦味を少なくし、花びらの部分が大きくなるよう品種改良した菊のことで、刺し身のつまに用いる「小菊(こぎく)」や、おひたしや天ぷらで使う大輪の「延命楽(えんめいらく)」、明るい黄色の「阿房宮(あぼうきゅう)」などの種類があります。
●小菊(こぎく)・・刺し身などの彩りとして添えられる小さい食用菊。「こまり」「秋月」「金綿」など5品種が時期を変えて栽培されている。
●延命楽(えんめいらく)・・山形県で「もってのほか」と呼ばれる紫色の食用菊。サイズが大きく、味・香り・食感ともに高く評価されている。「もってのほか」という名前は、「天皇の菊の御紋を食べるなんてもってのほか」に由来するもの。
●阿房宮(あぼうきゅう)・・明るい黄色が美しい食用菊で、青森県八戸(はちのへ)市が主な産地。延命楽よりも小さく、食感が柔らかい。
花言葉
菊の花言葉には、高貴、高尚、わずかな愛、破れた愛、誠実、真実があり、それぞれ次のような由来を持ちます。
●高貴、高尚・・皇室の紋章に用いられていることに由来する。菊は日本人にとって特別な存在で、品位・品格の証であった。
●わずかな愛、破れた愛・・キリスト教においての菊の「黄色」は、裏切り者のユダを連想し、ネガティブなイメージを伴うものだった。
●誠実、真実・・仏花や献花に用いられることの多い菊は、思いやりや慎ましさの象徴だと考えられていた。
■豆知識①『万葉集と菊』
日本人の心の花である「菊」は、実は日本の最古の歌集『万葉集』でほとんど詠まれていません。
「菊」が中国から日本にやって来たのは奈良時代末期のことで、その頃にはすでに『万葉集』の編纂(へんさん)は終わっていました。そのため、平安時代に編纂された『古今和歌集』では「菊」が多く詠まれているのに対し、『万葉集』ではまったくといって登場しないんです。
菊の紋章

「菊」は中国で、古くから邪気払いと長寿の効果がある格式高い花として人々に重宝されていました。
この思想が奈良時代に日本に伝わり、平安時代になると貴族を中心にして「菊」が大流行。着物の文様などに「菊紋」が用いられるようになります。
鎌倉時代に入ると、菊好きで有名な「後鳥羽(ごとば)上皇(※1)」が、自らの衣服や身の回りの物に「菊紋」を使用するようになり、1221年の「承久(じょうきゅう)の乱」で上皇が隠岐に流された後も「菊紋」はそのまま皇室で使われ続けます。
(※1)後鳥羽上皇【1180~1239】・・鎌倉初期の天皇。「承久の乱」で倒幕を企てるが、逆に幕府側に鎮圧され、隠岐島(おきのしま)に流される。「新古今和歌集」の編纂を藤原定家(ふじわらのさだいえ)らに命じ、日本文学史に大きな功績を残した。
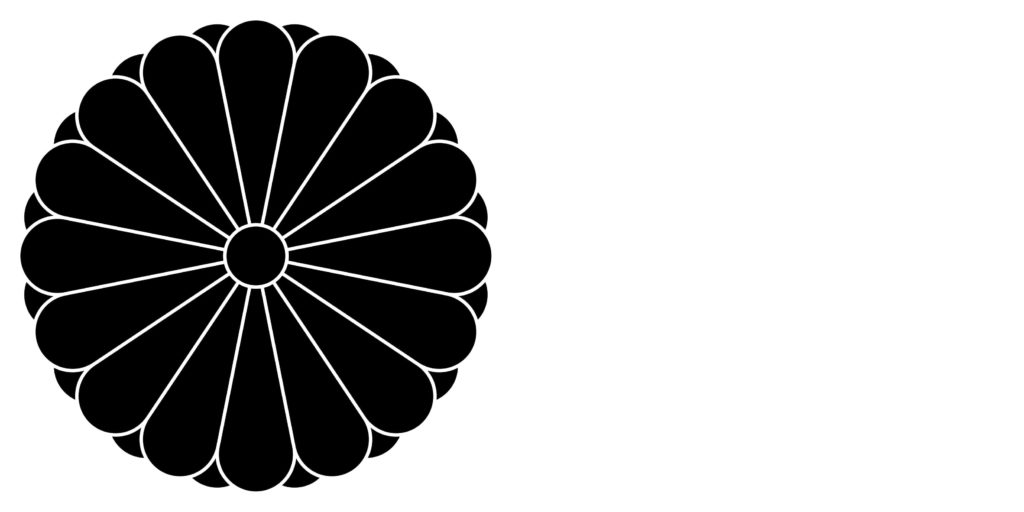
画像:『十六八重表菊』
現在の天皇家の紋章に使われている「菊花紋章(きくかもんしょう)/菊の御紋(きくのごもん)」は、菊の花の部分を図案化したもので、16枚の花弁が表を向いて重なっていることから、別名で「十六八重表菊(じゅうろくやえおもてぎく)」と呼ばれています。
明治維新の後の1869年に、天皇のみが使用できる紋章として公式に認定され、過去には、足利尊氏などの有名な武将も使用していました。

画像:『十六一重表菊』
また、パスポートの表紙に上図のような「菊紋」が描かれていますが、こちらは「一重菊(十六一重表菊)」と呼ばれるもので、「菊花紋章」とはデザインが少し異なります。
■豆知識②『弔事と菊』
お葬式の供え花としてのイメージが強い菊。お葬式やお仏壇などの弔事で菊の花が使われているのは、次のような理由があるからです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●菊の香りがお香に似ている。
●枯れても散らかることがなく、片付けやすい。
●邪気払いや長寿をもたらす縁起の良い花だから。
●皇室の紋章に使われている花なので、格調が高く厳粛。
重陽(ちょうよう)の節句

歴史・由来
旧暦9月9日の「重陽(ちょうよう)の節句」(別名:菊の節句)は、五節句の最後を締めくくる節句で、秋の収穫を祝うとともに、お神酒(みき)に菊を添えて無病息災や不老長寿を祈願する年中行事の一つです。
古来中国に、小高い山に登って邪気払いと延寿の効果がある「菊酒(きくざけ)」を飲んで不老長寿を願う風習があり、これが平安時代に日本に伝わって、貴族の宮中行事として定着したと考えられています。
ちなみに「重陽の節句」の「重陽」は「陽数が重なる」の意味で、「陽数」とは「奇数」のことです。
中国の陰陽思想において「奇数」は良いことを意味する「陽数」を、「偶数」は悪いことを意味する「陰数」を表していて、陽数の重なる日は、めでたい反面で不吉なことも起きる日とされていました。
そのため、陽数の重なる「五節句」に邪気払いの儀式が行われるようになり、中でも一番大きな陽数(=9)が重なる「9月9日」を特別に「重陽の節句」と定め、不老長寿や子孫繁栄を願うようになったのです。
■豆知識③『五節句(ごせっく)』
「節句(せっく)」とは、五穀豊穣や無病息災を願って邪気を払う季節の重要な「節目」のことで、江戸時代に幕府に定められた5つの節句のことを特に「五節句(ごせっく)」(下記参照)と言います。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
●人日(じんじつ)の節句(1/7)・・別名「七草の節句」。邪気払いと薬効のある七草粥を食べて無病息災を祈願する。
●上巳(じょうし)の節句(3/3)・・別名「桃の節句」。女の子の健やかな成長を祝う日で、お雛様を飾ったり、桃の花・菱餅を供えたりする。
(▶▶関連記事:【3月行事】ひなまつりと上巳(じょうし)の節句)
●端午(たんご)の節句(5/5)・・別名「菖蒲の節句」。男の子が勇ましく丈夫に育つことを願う日で、粽(ちまき)や柏餅を食べたり、鯉のぼりをあげたりする。
(▶▶関連記事:【5月行事】端午(たんご)の節句と八十八夜)
●七夕(しちせき)の節句(7/7)・・別名「笹の節句」。天に伸びる神聖な笹に短冊を結んで願いを託す日。
(▶▶関連記事:【7月行事】七夕の節句と土用の丑の日)
●重陽(ちょうよう)の節句(9/9)・・別名「菊の節句」。長寿の効果がある菊酒を飲んだり、菊の花を鑑賞したりする。
(▶▶関連記事:【9月行事】中秋の名月(十五夜)と重陽の節句)
行事・風習

「重陽の節句」の行事・風習には、以下のものがあります。
菊酒(きくざけ)
蒸した菊の花びらを器に入れて冷酒をそそぎ、一晩置いて香りを移すことで出来るのが「菊酒(きくざけ)」です。「菊」を鑑賞しながらこのお酒を飲むと長寿になると考えられていました。
現代では、「菊」の花びらを散らした「杯(盃)」に冷酒を注いで飲むスタイルが主流となっています。
菊湯・菊枕(きくゆ・きくまくら)
重陽の節句には、血行促進・保温効果がある「菊」を湯船に浮かべた「菊湯(きくゆ)」に入ったり、安眠効果の高い「菊枕(きくまくら)」(=乾燥した菊の花びらを詰めた枕)で眠る風習がありました。
着せ綿(きせわた)
「着せ綿」は日本独自の風習で、重陽の節句の前日の晩に「菊」に綿を被(かぶ)せ、当日の朝に、夜露と香りの染み込んだ綿で身体を拭いて不老長寿を願うというものです。
江戸時代に細かな決まり(=白菊には「黄色い綿」、黄菊には「赤い綿」、赤菊には「白い綿」)が設けられましたが、明治以降からはそのルールがなくなり、現代に至っては「着せ綿」の風習そのものが廃れてしまっています。
茱萸嚢(しゅゆのう)
重陽の節句には、「呉茱萸(ごしゅゆ)の実」(=グミの実)を緋色の袋に入れた「茱萸嚢(しゅゆのう)」を身に着けて飾るという風習があります。
これは中国の故事に由来するもので、「呉茱萸の実の入った袋をさげて山の頂で酒を飲んだところ、疫病神が退散した」という説話をもとにして、日本でも取り入れられるようになったと言われています。
菊合わせ
育てた菊を持ち寄って、その美しさを競い合う催しのことを「菊合わせ」と言い、現在でも各地で菊の鑑賞会や品評会が行われています。
栗ごはん

栗の収穫時期にあたる「重陽の節句」は、別名で「栗の節句」と呼ばれていて、地域によっては、秋の豊穣を祝って「栗ごはん」を食べることがあります。栗はとても栄養価が高く、疲労回復効果のあるビタミンB1やビタミンCを多く含んでいます。
くんち
『おくんちにナスを食べると中風(※2)にならない』という言い伝えにちなんで、「重陽の節句」には、焼きナスなどのナス料理が好んで食されていました。
(※2)中風(ちゅうふう)・・発熱・悪寒・頭痛などの症状の総称のこと。漢字は「悪風に中(あた)る」にちなんだもの。
「くんち」とは旧暦9月9日(くにち)に行われる収穫祭のことで、有名な「くんち」に、長崎の「長崎くんち」と佐賀の「唐津くんち」があります。
おわりに
いかがでしたでしょうか。
では、最後に内容をおさらいしましょう。
■秋を代表する花の「菊」には、日本で作られた「和菊」と欧米で作られた「洋菊」の2種がある。
■「菊」は高貴・高尚の象徴として、皇室や皇族の紋章に用いられていて、その名を「菊花紋章/十六八重表菊」と言う。
■五節句の一つである「重用の節句」は、無病息災・不老長寿を願う伝統行事で、「重陽」とは、「陽」数が「重」なるという意味。
■「重陽の節句」の行事・風習には、「菊酒」「菊湯」「菊枕」「着せ綿」「菊合わせ」などがある。
「菊」は、天皇家の紋章やパスポートに描かれるほどに、日本人にとって非常に親しみ深い存在なのに、肝心の「重陽の節句」の知名度が低いというのはどこか寂しい気がしますね。
そんな可愛そうな「菊」のためにも、今回ご紹介した五節句の「重陽の節句」と天皇家の「菊花紋章」は、ぜひ忘れずに覚えて帰ってください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
![]()
▼花札の歴史や雑学をもっと知りたい方はこちら▼
■花札の絵柄の意味と由来 |札の名前からみる日本の風物詩
■任天堂と花札の関係|歴史と企業哲学からみる成功のルーツ
■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと
▼「こいこい」「花合わせ」の詳しい遊び方を知りたい方はこちら▼
■「こいこい」のルール(遊び方)と役一覧・点数表|月札の覚え方
■「花合わせ」のルール(遊び方・3人)|出来役一覧・点数早見表
▼花札の基礎用語辞典はこちら▼
■花札の基礎知識|花札用語の読み方と意味を知ろう
▼おすすめ無料花札アプリはこちら▼
■【2024年】無料花札アプリおすすめ9選|オフライン・オンライン対応



コメント