
こんにちは、
りんとちゃーです。
花札の4月札で「藤(フジ)」と一緒に描かれる「ホトトギス」。

(左から順に「藤に不如帰(ホトトギス)」「藤に短冊」「藤のカス」「藤のカス」)
夏を代表する渡り鳥の「ホトトギス」は、カッコウと良く似た外観をしていて、「種間托卵(しゅかんたくらん)」という変わった習性を持っています。
また「ホトトギス」は、夏の季語にもなっていて、万葉集や和歌・俳句のモチーフとしても数多く登場します。
記事では、以下のことをまとめています。
■ホトトギスの生態と特徴、托卵の習性
■漢字表記の由来・語源
■和歌・俳句の中のホトトギスと戦国武将の名句
和歌や俳句・歴史などに触れながら、「ホトトギス」についての理解を深めていきましょう。
▼ホトトギスと一緒に描かれている「藤(フジ)」についての記事はこちら▼。
■関連記事:「藤(フジ)」の特徴・種類と花言葉|マメ科植物に学ぶ『マメ』知識
ホトトギス

■基本データ
分類:カッコウ目カッコウ科
学名:Cuculus poliocephalus
和名:ホトトギス
漢名・異名:不如帰、時鳥、子規、杜宇、郭公など
英名:Lesser Cuckoo
生息地:中国、インド、アフリカなど
食性:蛾の幼虫や昆虫などを好む
生態・特徴
5月頃に日本にやって来る「ホトトギス」は、夏を代表する渡り鳥であり、その外観はカッコウに非常によく似ています。体長は28cmほどで羽は黒く、縞模様のある白い腹部と青灰色の背中、目の周りの黄色いアイリングが特徴的です。
「ホトトギス」は主に、ウグイスが生息する森林やその周りの藪(やぶ)などに暮らしており、警戒心が強いせいか、その姿を近くで見ることはなかなかできません。
また、「キョ、キョ、キョキョキョキョ」といったユニークな声で鳴く特徴があり、地域によってはその鳴き声を「本尊かけたか」「テッペンカケタカ」「特許許可局」などに聞きなしています(※豆知識①参照)。

ぼくの鳴き声は
こんなのだよ↓↓
■豆知識①『聞きなし』
鳥のさえずりを人の言葉に置き換えることを「聞きなし」と言い、鳴き声を効率よく覚える方法として用いられています。以下は、有名な鳥の「聞きなし」の一覧になります。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
▶つばめ(燕)・・「土食って虫喰って、口渋~い」
▶うぐいす(鶯)・・「法、法華経(ホ―ホケキョ)」
▶コノハズク・・「仏法僧(ブッポウソウ)」
▶ヒガラ・・「貯金貯金(チョキンチョキン)」
▶ホオジロ・・「一筆啓上仕り候(いっぴつけいじょうつかまつりそうろう)」
▶センダイムシクイ・・「焼酎一杯グィ―ッ」
習性

「ホトトギス」は「托卵(たくらん)(※1)」という変わった習性を持っていて、ウグイスの巣に自分の卵を産んで、ウグイスに子どもを育てさせています。
(※1)托卵・・他の生物に自分の子どもを育てさせる習性のことで、同種の別の親に自分の子どもを育てさせる「種内托卵(しゅないたくらん)」と、異なる種の親に自分の子どもを托す「種間托卵(しゅかんたくらん)」の2種類がある。ホトトギスの「托卵」はこの「種間托卵」にあたる。
托卵された「ホトトギス」の卵は、ウグイスの卵より先に孵(かえ)り、その「ホトトギス」の子どもによって、周りのウグイスの卵は捨てられてしまいます。結果、ウグイスは「ホトトギス」の子どもを自分の子どもだと思い込んで世話をすることになるのです。
「ホトトギス」が托卵をする理由についてはよく分かっていませんが、一説によると、「ホトトギス」は体温変化が大きく、卵を一定温度で温めることができないからだと言われています。
由来・語源
20以上ある「ホトトギス」の漢字表記・異名のうち、代表的なものを以下にまとめました。
ホトトギス
読みの「ホトトギス」は、ホトトギスの鳴き声「ホトホト」と、鳥を意味する接尾語の「ス」を組み合わせたものです。
時鳥
「ホトトギス」の渡来する時期がちょうど田植えを始める頃にあたり、「田植えの時期の到来を告げる鳥」の意味で「時鳥(ときつどり)」と呼ばれています。また、同じ意味合いで「勧農鳥(かんのうちょう)」「早苗鳥(さなえどり)」と表記することもあります。
この「時鳥」を使って「ホトトギス」の特徴を上手く表現したのが、古今和歌集に見られる次の和歌で、田植えの監督者である田長に向けて「ホトトギス」が、「田植えを早くするように!」と急き立てている様子が目に浮かびます。
『いくばくの 田を作れば 時鳥(ほととぎす) しでの田長(たおさ)に 朝な朝な鳴く』――藤原敏行※2
(※2)藤原敏行(ふじわらのとしゆき)【?-791】・・平安時代前期の貴族・歌人・書家。三十六歌仙の一人として「古今和歌集」に28首の和歌をのこす。個人の歌集に「敏行集」がある。
不如帰
古代中国の蜀(しょく)の王であった「杜宇(とう)」が、ある時、不品行を働いたという理由で王位の座を退位させられます。
その際に「杜宇」は復位を強く望みますが、まったく聞き入れてもらえず、結局、国を離れることに。その時に彼が、泣きながら「国へ帰りたい(=帰るに如かず)」と嘆いた逸話が「不如帰」の語源になっています。
杜宇
農耕を指導して蜀の国を発展させた「杜宇」が、死後にホトトギスの化身となって人々の前に現れ、農耕の始まる時期を教え諭したという話にちなんで、彼の名前が当てられています。
子規
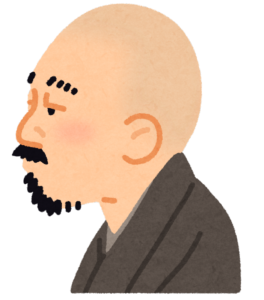
「不如帰」という言葉が、ふるさとを離れた旅人に「帰心(=故郷に帰りたいと思う心)」を想起させることに由来して「不如帰」が「思帰(しき)」へと変化。それがさらに転じて「子規(しき)」になったと考えられています。
ちなみに、正岡子規(※3)の名前の「子規」もこの異称からとったもので、血を吐いたような赤い口の「ホトトギス(子規)」の姿を、結核による吐血で苦しむ自身の姿と重ね合わせたものだと言われています。
(※3)正岡子規(まさおかしき)【1867-1902】・・明治時代の俳人・歌人・国語研究家。愛媛県松山市生まれ。当時廃れていた俳句・和歌に革新をもたらし、俳句界の繁栄に大きく貢献した。「柿食えば鐘が鳴るなり法隆寺」の句で有名。
和歌と俳句

夏の季語になっている「ホトトギス」は、万葉集や和歌・俳句などにも多く登場します。ここでは、その中の代表的な3首を紹介したいと思います。
①『ほととぎす 鳴きつるかたを 眺むれば ただ有明(ありあけ)の 月ぞ残れる』――後徳大寺左大臣
この歌は、百人一首(81番)に詠まれている「藤原実定(ふじわらのさねさだ)※4」の有名な和歌で、意味は「ホトトギスの鳴いたほうを眺めてみるがその姿は見えず、ただ明け方の月が淡く空に残っているだけだ」です。
(※4)藤原実定(ふじわらのさねさだ)【1139-1191】・・平安時代後期の歌人。通称「後徳大寺左大臣」。百人一首の選者「藤原定家(ふじわらのさだいえ)」の従兄弟にあたる。蔵書家で才学に富み、詩歌や今様(いまよう)、神楽(かぐら)・弦楽などに優れていた。
②『目には青葉 山ほととぎす 初鰹(はつがつお)』――山口素堂
この句を詠んだのは俳人の山口素堂(やまぐちそどう)※5です。
(※5)山口素堂(やまぐちそどう)【1642-1713】・・江戸時代中期の俳人。甲斐国(山梨県)出身。松尾芭蕉と親交が深く、蕉風の確立に寄与した。漢学や俳諧、茶道・書道を身につけた教養人。
夏の季語が3つ含まれる「季重(きがさ)なり」は、一般的に俳句の世界では「禁じ手」とされていますが、それでもなおこの句が成立しているのは、「目に鮮やかな青葉」「美しい鳴き声のホトトギス」「美味しい初がつお」といった「初夏の新鮮さ」を象徴する3つをありのままに受け止め、あふれんばかりに作者が喜びを表現しているからでしょう。
③『帰ろふと 泣かずに笑へ 時鳥(ほととぎす)』――夏目漱石
正岡子規の大親友であった夏目漱石が、入院中の子規のお見舞いとして詠んだ有名な句です。2人の深いつながりと、漱石から子規への励ましのメッセージが強く読み取れます。
戦国武将とホトトギス

戦国時代を代表する三大武将の「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」の性格・人間性を表した有名な川柳に「ホトトギスの句」があり、それらの句は、江戸時代後期の平戸藩主・松浦静山(まつらせいざん)※6が書いた随筆「甲子夜話(かっしやわ)」の中に登場します。
(※6)松浦静山(まつらせいざん)【1760~1841】・・江戸時代中後期の大名で、肥前国(長崎・佐賀県)平戸藩の第9代藩主。本名は「松浦清」。江戸期の日本を描いた随筆集「甲子夜話」の著者として知られる。文武両道に励み、数多くの名言を残した。
以下は、3武将の「ホトトギスの句」の簡単なまとめになります。
①『鳴かぬなら 殺してしまえ ホトトギス』 ――織田信長
▶▶鉄砲などの革新的武器をいち早く取り入れ、軍事に改革を起こしたことで知られる織田信長の、短気で残虐性のある性格を象徴する句です。
②『鳴かぬなら 鳴かせてみよう ホトトギス』 ――豊臣秀吉
▶▶策略家で人心掌握術に長けた豊臣秀吉。農民から天下人へと知恵を駆使して成り上がった、彼の要領の良さをこの句は示しています。
③『鳴かぬなら 鳴くまで待とう ホトトギス』 ――徳川家康
▶▶長きに渡る江戸幕府の礎を切り開いた初代将軍の徳川家康。堅実で忍耐強く、天下が取れる時期まで辛抱強く待ち続けた、彼の性格を上手く表現しています。
おわりに
いかがでしたか。
では、内容をおさらいしましょう。
■夏を代表する渡り鳥の「ホトトギス」は、鳴き方が特徴的で、その外観はカッコウに良く似ている。
■「ホトトギス」は、自分の子どもを他の生物に育てさせる「種間托卵」の習性を持ち、育て親として「ウグイス」を選んでいる。
■「ホトトギス」の異名・漢字表記には、「時鳥」「不如帰」「子規」などが存在し、それぞれに由来がある。
■夏の季語でもある「ホトトギス」は、和歌・俳句などでよく用いられる。
■戦国時代の三英傑「織田信長」「豊臣秀吉」「徳川家康」の性格を端的に表現した「ホトトギスの句」という有名な川柳がある。
「ホトトギス」は、文学作品・和歌などのモチーフとして使われるほどに、古くから日本人に愛されてきた馴染み深い鳥です。
近年の都市化の影響を受け、街なかではあまり声を聞くことができなくなりましたが、自然の多い場所であれば、まだまだその姿を見ることができます。
旅行に行った際には、ぜひ「ホトトギス」のいる場所を探してみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
![]()
▼ホトトギスと一緒に描かれている「藤(フジ)」についての記事はこちら▼
■「藤(フジ)」の特徴・種類と花言葉|マメ科植物に学ぶ『マメ』知識
▼花札の歴史や雑学をもっと知りたい方はこちら▼
■花札の絵柄の意味と由来 |札の名前からみる日本の風物詩
■任天堂と花札の関係|歴史と企業哲学からみる成功のルーツ
■花札の歴史|日本の伝統的「かるた」の繁栄と衰退の足あと


コメント