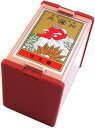こんにちは、
りんとちゃーです。
花札をはじめとした、日本のカードゲームの元祖となる「かるた(歌留多・骨牌)」。
安土桃山時代に起源を発する「かるた」は、「幕府に取り締まられたり、国に税を課せられたり」と歴史的に非常に数奇な運命をたどります。
記事では、以下のことをまとめています。
■かるたの起源と発祥地
■「かるた賭博禁止令」の発布と変化型かるたの誕生
■「骨牌(こっぱい)税法」の制定とかるた文化の衰退
「花札」の歴史を紐解きながら、そのルーツに迫ってみましょう。
かるたの起源・発祥地

時はさかのぼること、安土桃山時代。
ポルトガル人宣教師によって、鉄砲やキリスト教と一緒に日本に初めて「カードゲーム(※1)」が伝えられます。
(※1)「カードゲーム」はポルトガル語で「carta(カルタ)」と表記し、これが「かるた」の語源となった。
当時ポルトガルから伝えられたものは、「かるた」と言うより「トランプ」に近いもので、「4つのスーツ【=紋標(聖杯・剣・棍棒・金貨)】」に、「1~9・J・Q・K」の12の数字・アルファベットが描かれた、計48枚(4✕12)のカードセットでした。
これが九州の三池(みいけ)地方(現在の福岡県大牟田市※2)で印刷され、日本で初めてのかるた「天正カルタ」が誕生します。
(※2)大牟田(おおむた)市・・国産かるた発祥の地。1991年に「三池カルタ記念館」を建設、2006年に「歴史資料館」と統合して「三池カルタ・歴史資料館」となった。
「かるた賭博禁止令」と変化形かるた

江戸時代になると、賭博(とばく)目的で「かるた」が使用されるようになり、これを由々しき事態だと考えた江戸幕府は、賭博としての「かるた」を禁止する「かるた賭博禁止令」を発布します。
それを受けて町人たちは、外見上「賭博」だと分からないようにするために「花札」という「抜け道かるた」を考案(※3)。法令をかいくぐって賭博を続けようとします。
(※3)花札以外にも、様々な「抜け道かるた」が生み出され、代表的なものでは、カードの枚数を48枚から75枚に増やした「うんすんカルタ」や、百人一首の原形の「歌かるた/いろはかるた」が挙げられる。
「花札」は「かるた」に使われる「12の数字」に「12の花」を割り当てたもので、札の絵柄の図案には、当時教育用に使われていた「和歌かるた」が参照されました。
こうして、外見上は賭博と分からなくなった「かるた(花札)」ですが、幕府の目のある中で堂々と遊ぶわけにはいかず、隠れて遊ぶために店の奥に「賭博場(とばくじょう)」が設けられることになります。
この「賭博場」に案内してもらうときの合図となったのが「鼻をこする」(鼻が『花=花札』を暗示)動作で、今の花札のパッケージに「天狗」が描かれているのは、この時の「鼻」の隠語表現にちなんで、花札販売店の店先に「天狗(=鼻)」が掛けられていたからです。
花札の解禁と「骨牌(こっぱい)税法」

明治時代になって「文明開化」が起きると、西洋文化を代表する遊戯の「西洋トランプ」が日本に流入し、「あそび目的ならトランプ類の使用も問題ない」という西洋の考え方に倣い、日本でもあそび目的での花札の使用が認められるとになります。
こうして花札の販売が解禁され、庶民のあいだでも花札が遊ばれるようになるのですが、それも束の間。1902年になると「骨牌(こっぱい)税法」いう法律が制定され、賭博使用の可能性のあるカードゲーム(麻雀牌・トランプ・花札など)すべてに税が課せられてしまいます。
この「骨牌税法」の課税対象は「消費者」ではなく「製造企業」であったため、「花札」や「かるた」を扱う会社は大打撃を受け、次々に倒産。
結果、「花札」をはじめとした「かるた文化」が急激に衰退し、各地にあった「地方札」や「伝統的な遊び方」が失われていくことになったのです。
■豆知識『トランプと呼ぶのは日本だけ!?』
日本では、カードを使用する室内玩具のことを「トランプ」と言いますが、本来の英語の「トランプ(Trump)」は「奥の手・切り札」を意味し、カードを指すものではありません。
実は、江戸時代に日本に滞在していたポルトガル人が、カード遊びをしながら、奥の手・切り札の意味で「トランプ!」とよく口にしていて、それを聞いた日本人が「カード遊びの名前はトランプだ」と勘違いして覚えてしまった歴史的経緯があるのです。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
では、内容をおさらいしましょう。
■「かるた」の起源となったのは安土桃山時代に伝来したボルトガルの「カードゲーム(=carta)」で、国産かるたの発祥地は九州の三池地方(福岡県大牟田市)にある。
■江戸時代に、賭博目的の使用を制限するために幕府が「かるた賭博禁止令」を発令した。
■賭博目的の「かるた」の抜け道として「変化型かるた(=花札)」が生まれ、その遊び場として「賭博場」が設けられた。
■文明開化によってあそび目的での花札の使用が容認され、花札が解禁された。
■1902年に、賭博使用の可能性があるカードゲームに税を課す「骨牌(こっぱい)税法」が制定され、製造企業が大打撃。「かるた文化」が衰退することになった。
歴史的に見ると衰退し遊ばれなくなった「花札」ですが、最近では、テレビやアニメ・映画の中に登場したり、パソコンやスマホで簡単に遊べるようになるなどして、その人気が再び高まりつつあります。
2人でする「こいこい」や3人での「花合わせ」など、様々な遊び方があるので、興味を持った方は、ぜひ実際の「花札」を手にとって遊んでみてください。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
![]()
▼「花合わせ」「こいこい」の詳しい遊び方・役を知りたい方はこちら▼
■「こいこい」の遊び方(ルール)と役・点数一覧
■「花合わせ」(3人)の遊び方(ルール)と得点数表・役一覧
▼花札の歴史や絵柄の意味・由来などに興味のある方はこちら▼
■花札の絵柄の意味と由来 |札の名前からみる日本の風物詩
■ゲーム会社「任天堂」と花札・トランプの関係|始まりは小さな花札屋
▼おすすめ無料花札アプリはこちら▼
■【2024年】無料花札アプリおすすめ9選|iPhone・Android対応
▼花札の基礎用語辞典はこちら▼
■花札の基礎知識|花札用語の読み方と意味を知ろう