
こんにちは、
りんとちゃーです。
数ある重松清の作品の中で、名作と評される短編小説「青い鳥」。
吃音症を持ち、言葉がつっかえて上手く話せない非常勤講師の村内先生には、生徒に伝えたい「たいせつなこと」があります。
そばに寄り添って真摯に向き合ってくれる先生との出会いを通して、次第に傷ついた心を癒やしていく、悩みを抱えた様々な少年・少女たち――。
何度も読み返したくなるエピソードの中に、胸に響く至極の言葉が詰まった本短編集は、未読の方にこそ読んでほしい作品です。
記事では以下のことをまとめています。
■本の内容紹介と収録作品
■収録作品全8編のあらすじと感想
■著者「重松清」の紹介・プロフィール
ストーリーの把握や内容のおさらいとしてご活用ください。
本の内容紹介と収録作品
村内先生は、中学の非常勤講師。国語の先生なのに、言葉がつっかえてうまく話せない。でも先生には、授業よりももっと、大事な仕事があるんだ。いじめの加害者になってしまった生徒、父親の自殺に苦しむ生徒、気持ちを伝えられずに抱え込む生徒、家庭を知らずに育った生徒──後悔、責任、そして希望。ひとりぼっちの心にそっと寄り添い、本当にたいせつなことは何かを教えてくれる物語。
―――新潮文庫「青い鳥」内容紹介より
この短編集には次の8編が収録されています。
■収録作品
・ハンカチ
・ひむりーる独唱
・おまもり
・青い鳥
・静かな楽隊
・拝啓ネズミ大王さま
・進路は北へ
・カッコウの卵
以下は、収録作品8編の簡単なあらすじと感想になります。
あらすじと感想
ハンカチ

■あらすじ
「学校の制服にポケットがあって良かった・・」。クラスのアンケートにそう書く私。実は私は、あることがきっかけで場面緘黙症になり、学校で上手くしゃべれなくなってしまったのです。
そんな私にとって、声にならない言葉をすべて吸収してくれるハンカチは必需品でもありました。ある日、職員室に呼ばれた私は、代理担任の村内先生から「どうして卒業式に出たくないと日記に書いたの?」と尋ねられて――。
場面緘黙症という特定の場でしゃべれなくなる病気に悩み、その緊張を解消するためにいつもハンカチを握りしめていた主人公の少女。
少女はもともとおしゃべりな子でしたが、他人の悪口を平気で言うことが多かったため、ある日先生から、みんなの前で謝罪するように強要されます。そして、そのことが原因で上手く話せなくなってしまったのです。
物語では、前の担任の復帰で、代理担任の村内先生が卒業式でみんなの名前を呼ぶ大任から外されるのですが、そんな中で私は、式本番で村内先生に自分の名前を呼んでほしいと訴え続けます。
たとえ上手くしゃべれなくても、大切なことは自分で伝えなければならない――、そう先生が教えてくれたからこそとった行動でした。
当然、先生が呼んだ名前はつっかえたものになり、場には決まりの悪い空気が流れます。でも、村内先生の拙い言葉は、私にとっては掛け替えのない大切なものになっていました。
言葉にできないことに悩む少女が、吃音の先生と出会い大切にすべきことを知る――。小説の導入にふさわしい、短いながらも心に触れる素敵なストーリーだったと思います。
ひむりーる独唱

■あらすじ
久しぶりに学校にやって来た僕は、クラスのみんなの態度がよそよそしいことに気付きます。3ヶ月の間にすっかり変わってしまった僕の周りの世界──。担任の先生はいなくなって、代わりに村内先生という吃音の先生がいて・・。
実は、前の担任の先生がいなくなったのはすべて僕のせいで、3ヶ月前のあの日、僕は先生をナイフで刺してしまったのです。
クラスで疎外感を覚え居場所を失い、誰ともしゃべらずに孤独な日々を送っていた少年。
なぜ先生を刺してしまったのか自分でも分からず、家族や友人からも距離を置かれていた少年のもとへ、ある日、先生が現れ「草野心平の詩にきみがいる」と伝えます。
それは「ひむりーる」という白いカエルでした。
「みんな孤独で。
みんなの孤独が通じあふたしかな存在をほのぼの意識し
うつらうつらの日を過ごすことは幸福である。」
――草野心平「ごびらっふの独白」より
物語やポエムには、言葉以上の意味があります。
印象的な草野心平の詩を通して先生が少年に投げかけたメッセージ。
誰もが孤独を感じ、周りと通じ合いたいと思いながら、日々を過ごしていく・・。そんな中にもささやかな幸福がある。
解釈は人によってさまざまですが、思春期を生きる少年には、きっとどの言葉よりも深く響いたのだと思います。
おまもり

■あらすじ
交通事故で入院した友だちの清水ちゃんのもとに見舞いにやって来た私は、彼女から「当て逃げした犯人が絶対許せない」と話を聞かされます。その言葉が胸に刺さって離れない私。実は、父親が自動車事故を起こし、清水ちゃんの言う犯人と同じ加害者になってしまっていたのです。
本作では、被害者ではなく加害者家族の立場から見た世界が描かれ、読んでいる私たちは異なる視点でストーリを追うことになります。
罪は許されることではなく、一生かけてでも償わなければならないことです。しかし、加害者を裁くことだけですべてが解決するわけではありません。
「罪を憎んで人を憎まず」の言葉にあるように、大切なのは、被害者だけでなく加害者にも目を向け、なぜそのようなことが起きたのか、どうすれば悲劇を二度と起こさないようにできるのか、それを考えることにあるのでしょう。
物語の冒頭では被害者遺族に邪険に追い返されていた父親ですが、最後には遺族の家にあがることを許されることになります。
「父親をどうか許して欲しい」と願う私の思いを汲むようにして訪れた物語のラスト──。罪を犯した人間に救いを差し伸べる展開に、思わず涙腺が緩んでしまいました。
青い鳥
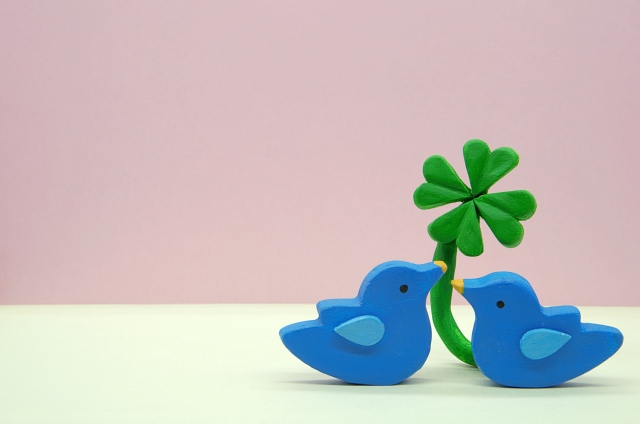
■あらすじ
僕たちは罰を受けている──。村内先生は、教室で空席となった野口くんの机の前に立ち、彼がいるかのように振る舞います。きっとそれは僕たちに向けられているのだろう・・、少年はそんなふうに考えます。そう、少年たちは野口くんをいじめた主犯グループだったのです。
学校で起きたいじめ事件。村内先生はその罪の重さを忘れさせまいと僕たちに罰を与えます。
そんな先生が物語の中で、「いじめることと人を嫌うことの違いがわからない」と口にする僕に向けてこう言います。
「人を嫌うから、人数がたくさんいるからいじめになるんじゃない。人を踏みにじって苦しめたり、苦しんでいる人の心の声を聞かないからいじめになるんだ──。」
人間である以上、人に嫌悪感を抱くことはもちろんあります。問題なのはそれを行動や態度に出して相手を傷付けたり、傷付いて苦しんでいる人の気持ちを理解しようとしないことにあるのでしょう。
いじめた事実に向き合ってもらおうと、生徒に対して本気でぶつかる村内先生。
青い鳥BOXの設置や反省文などの表面的な解決法にひっかかりを覚えていた僕にとって、先生が見せたその真剣な姿勢は、本当の意味で求めていた答えだったのかも知れません。
静かな楽隊

■あらすじ
中学で私は、クラスで一番きれいなあやちゃんのご機嫌をとるようなことばかりしていました。頭の良いあやちゃんは、自分の気に入らないものを徹底的につぶし、クラスの中には、いつの間にか彼女の帝国のようなものが築かれていました。
私はそんな彼女と話をするのがツラくなってきて、ふと、小学校の同級生のトロちゃんのことを思い出します。
クラスの中で支配的な態度をとるあやちゃんの言動に戸惑い、彼女と話を合わせられないことと、周りと上手く同調できないことに悩む少女。そんな彼女が村内先生との出会いを通して、次第に心の平穏を取り戻していきます。
物語で印象に残ったのは、村内先生のつっかえをカスタネットにたとえて、少女が想像の中で合奏を始めるシーンで、特に結末の「私・トロちゃん・先生の3人で誰にも聞かれずに静かな合奏ができたらいいな」と話すくだりに、表題の「静かな楽隊」との繋がりを強く感じました。
拝啓ネズミ大王さま

■あらすじ
飼っているハムスターのネズミ大王に向かって、いつものように学校での不満や愚痴をこぼす少年。ハムスターは父親が買ってくれたものですが、その父親は飛び込み自殺をして死んでしまったため、今はもういません。父は、会社で責任の強い仕事を任され、その重みで心が押し潰されてしまったのです。
主人公の少年は、友情・団結・思いやりなど、綺麗ごとばかりを並べる学校の方針が気に入らず、いつも不満をこぼしていました。そして、その歪んだ考え方のせいでクラスの中でどんどん孤立していきます。
ある日、何者かが学校に電話をかけたことで、開催を予定していたクラス対抗リレーが急遽中止になり、その犯人が誰かに見当がついた村内先生は少年に声をかけます。
少年を気遣って「つらかったんだなぁ、間に合って良かった・・」と優しく話しかける先生。その言葉に少年は救われ、罪を犯した自分を嫌うことなく、もう一度クラスのみんなとやり直すきっかけをつかみます。
大切な人を失ったことで生じた少年の悲しみや苛立ち、孤独などを、ペットのハムスター(ネズミ大王)への語りかけで表現したストーリーはどこかユーモラスで、主人公の罪や父の自殺というテーマの重みをあまり感じさせない読みやすさがありました。
進路は北へ

■あらすじ
私が出した年賀状に「教室の黒板は東西南北のどの方角にあるでしょう?」という意味の分からないことを書いて返してきた村内先生。実は私は、内部生優位のクラスの雰囲気や束縛の多い学校生活に息苦しさを感じていて、そんな自分の面倒を見てくれていたのが村内先生だったのです。
その後、進路面談が始まり、みんなと同じ内部進学ではなく高校受験を考えていた私は、クラスにいた外部生の古川さんのことを思い出します。
学校での集団生活に馴染めず、早くどこかへ逃げ出したいと切望する少女。
その思いは、方位磁石の「北(N)」を嫌いの「No」と考えることに始まり、窮屈な学校をパイプに棲むアナゴにたとえるなど、子どもならではのユーモラスな比喩で表現されていきます。
さらに、途中の「左利きの人を考慮にいれず、右利きの人の手元が影でかくれないようにするために、黒板は西を向いている」という話を始点に、内部生を軸にして動く不条理な学校像も描き出されます。
物語の中で印象に残ったのは、村内先生の次のセリフです。
「たとえ間違っていたとしても、皆が同じ方向を向いてるのに、一人だけそっぽをむくことはできないんだ。それはたいせつなことなんだ。」
たいせつなことが必ずしも正しいとは限らないこと。理不尽なことや納得できないことも時には受け入れなければならないこと――。残酷で厳しい社会の現実を表したこの言葉には、深く共感するものがありました。
カッコウの卵

■あらすじ
アパートで一緒に暮らす智恵子に「今日仕事帰りに村内先生に会った」と伝える主人公。先生は中学の頃の恩師で、周りのみんなが進学する中で社会に出る選択をした自分を後押ししてくれた唯一の人物でもありました。
主人公は、村内先生のことを智恵子にこう説明します。
誰かのそばいてくれる特別な先生であったこと。吃音があってうまくしゃべれないこと。そして、親に愛されずにひとりぼっちだった自分のことを「カッコウの卵」と呼んだこと──。
今までと異なり、最後の物語では教え子が恩師との思い出を懐かしむ形で話が紡がれていきます。
虐待を受け、人が信じられず、学校で孤立していた少年のそばにいつもいようとした村内先生。そんな先生が主人公を守るためにこんなことを言います。
「嘘をつくのは悪いことではなく、寂しいことなんです。ひとりぼっちになりたくないから嘘をつくんです──」
嘘を子どもからのSOSだとみなし、痛みや苦しみに寄り添おうとする村内先生。そんな先生の優しさと人間性があふれる言葉です。
また物語では、主人公と智恵子が質素ながらも仲睦まじい生活を送るのですが、その姿を見ているうちに、本当の幸せは豊かさにあるのではなく、大切な人と過ごすささやかな日常の中にあるのだということを改めて実感させられました。
本の作者「重松清」の紹介

重松清(しげまつきよし)
はこんな人だよ!
重松清さんは昔から大好きな作家の一人で、特に少年少女を主人公にした作品(「きよしこ」「くちぶえ番長」など)が大のお気に入りです。
彼の作品には、人の複雑な感情を繊細に描いたものが多く、傷ついたり・悩んだり・立ち直ったりと、ありのままの姿を見せる登場人物たちの存在も大きな魅力になっています。
ちなみに、作品の一部は学校の教科書にも採用されていて、「卒業ホームラン」「カレーライス」などは小学校の国語の授業でも習います。
また、映像化作品もあって、最近で言うと、2017年にドラマ化された「ブランケット・キャット」や、2018年に映画化された「泣くな赤鬼(短編小説「せんせい。」より)」などが有名です。
感受性の高い「少年少女」はもちろん、傷つきやすい「大人」もつい涙してしまうような感動作ぞろいの重松清文学。
興味を持たれた方は、他の作品も読んでみてはいかがでしょうか。
▼重松清のおすすめ作品はこちら▼
■重松清のおすすめ短編作品一覧|感動し泣ける名作7選(直木賞受賞作含む)
▼重松 清(しげまつきよし)▼
■人物・略歴
1963(昭和38)年、岡山県久米郡久米町生まれ。中学・高校時代は山口県で過ごし、18歳で上京、早稲田大学教育学部を卒業後、出版社勤務を経て執筆活動に入る。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表する。
■受賞歴
・1991年
『ビフォア・ラン』でデビュー。
・1999年
『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。
・2001年
『ビタミンF』で直木賞受賞。
・2010年
『十字架』で吉川英治文学賞受賞。
・2014年
『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。
■主な作品
『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。




コメント