
こんにちは、
りんとちゃーです。
表題作の「卒業」をはじめ、精選集に収められた「まゆみのマーチ」や、人生の卒業の「死」を題材にした「あおげば尊し」など、新たな旅立ちに向かおうとする4つの家族の『卒業の物語』を描いた短編小説「卒業」。
記事では以下のことをまとめています。
■本の内容紹介と収録作品
■収録作品4編のあらすじと感想
■著者「重松清」の紹介・プロフィール
ストーリーの把握や内容のおさらいとしてご活用ください。
本の内容紹介と収録作品
「わたしの父親ってどんなひとだったんですか?」ある日突然、14年前に自ら命を絶った親友の娘が僕を訪ねてきた。中学生の彼女もまた、生と死を巡る深刻な悩みを抱えていた。僕は彼女を死から引き離そうと、亡き親友との青春時代の思い出を語り始めたのだが――。悲しみを乗り越え、新たな旅立ちを迎えるために、それぞれの「卒業」を経験する家族を描いた4編。著者の新たなる原点。
―――新潮文庫「卒業」内容紹介より
この短編集には次の4編が収録されています。
■収録作品
・まゆみのマーチ
・あおげば尊し
・卒業
・追伸
以下は、収録作品4編の簡単なあらすじと感想になります。
あらすじと感想
まゆみのマーチ

■あらすじ
母が危篤になったと聞いて、ふるさとの病院を訪れた私。妹のまゆみと久しぶりに再会し、お互いの近況を報告し合っていると、まゆみから「入院中の母親によく『まゆみのマーチ』を歌ってあげていた」と伝えられます。
まゆみのマーチ・・、それは、母が小学生のまゆみのために作ってくれた歌でした。それを聞いた私は、学校に行かずに家に引きこもっている息子の亮太のことを思い出し、さらに子ども時代のまゆみに思いをはせて――。
死を間際にした母親の病床で妹のまゆみと再会し、彼女と話をする中で、息子の亮平との向き合い方についての手がかりを見出した私。
純粋な子どもの心はちょっとしたことで傷がついてしまいます。そして、そんな子どもの傷を治せる唯一の存在が親であり、たとえ非常識で、周囲を敵に回すようなことがあっても、親が自分の味方でいてくれ、守ってくれるというのは何よりもありがたいことです。
小難しい理屈など考えず、ただ親として子どもに愛情を言葉にして注ぐこと。その大切さを『まゆみのマーチ』の歌から教わった気がしました。
あおげば尊し
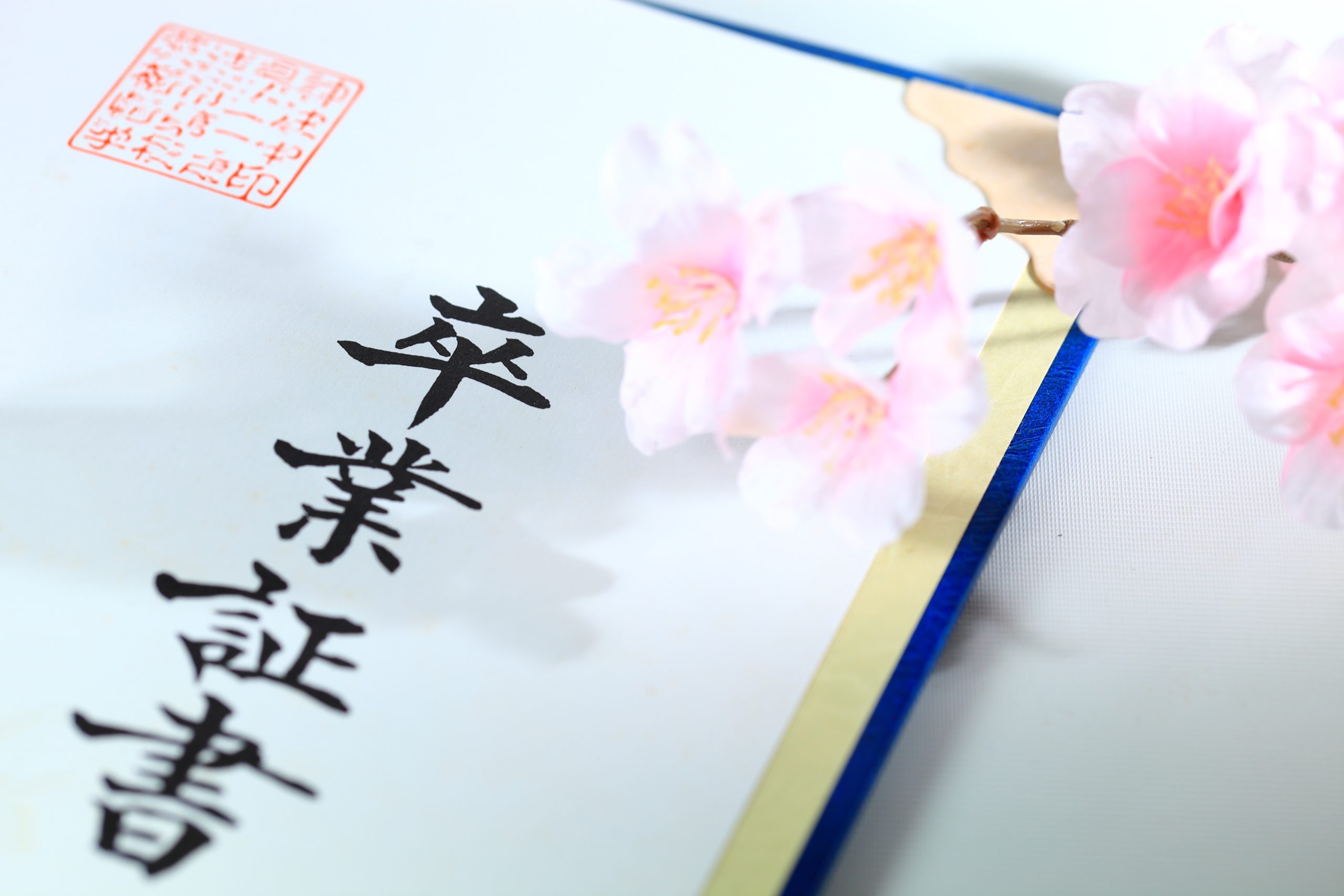
■あらすじ
学校で長年教師を勤めていた父が末期がんに冒され、医者から余命いくばくと聞かされた僕と母。家に帰って父をベットに寝かせると、父から「学校の卒業アルバムの入った本棚を持ってきて欲しい」と頼まれます。
父は規律を重んじる厳格な教師で、生徒から嫌われていました。父の教育論は『未完成な子どもたちが大人になれるように、社会のルールや厳しさを教えること』で、それを遵守するために、今まで多くの生徒たちに容赦ない処分を下してきました。だから大人になった教え子の中で、家を訪ねてきたものは一人もいません。父はそんな寂しい人間だったのです・・。
年老いて寝たきりになった親を介護し、その死を看取る時がやって来る――。そんな、普段目を背けている現実が突きつけられる二つ目の物語「あおげば尊し」。
作中の父の、体罰すら辞さない厳しい指導方法は、現代人からすると問題といえる非常識なものです。しかし、甘やかされて育った子どもというのは、社会に出たときに往々にして苦労するもの。
だから、時には心を鬼にして厳しく教える必要があり、そういう点で、父の教育論は間違っていなかったのでしょう。ただ、死を間際にしてもなお、教え子たちにそのことを理解してもらえないというのはとても寂しいものです。
物語の中で読者に投げかけられた「『死』とはいったい何か?」の問い。その問題の答えは、自分自身がその時を迎えるまで分かることがないのかも知れません。
卒業

■あらすじ
会社に突如やって来た、亡くなった親友・伊藤の娘・亜弥。中学生になった彼女の訪問に僕は戸惑い、なぜ会いに来たのかと理由を考えていると、彼女からこう切り出されます。「父親のことを知りたかったから――」。
さらに、自分が自殺未遂を起こしたことを告白し、「父親とそういうところも似るの?」と続けざまに聞いてきます。実は彼女の父親の伊藤は、会社の非常階段から飛び降りて死んでしまったのです。
前話の、最期まで教師として誇り高く生きようとする父親の姿を描いた物語とは対照的に、自らの命を断つことに人生の価値を見出だした一人の男と、残された家族の苦悩を描いた本作『卒業』。
主人公の僕は、親友の伊藤が自殺した理由をなかなか理解できないでいましたが、娘の亜弥や母親と会話をする中で、次第にその答えを見出だしていきます。
物語の終盤、主人公はこんなふうに語ります。
「コップは水が満杯になってからあふれるのではない。少し傾いただけでもこぼれることがある──。」
人は限界に達したときだけに死を選ぶわけではありません。誰しもがコップに一定量の水が貯まっていて、それぞれの振り幅で揺れています。そして、それが何かの拍子にこぼれてしまう、ということがあります。それくらい死は身近なものです。
しかし主人公は「それでも自ら死を選ぶことは決してあってはならない」と最後まで持論を主張し続けます。
捨てることや逃げることは卒業ではない、過去を振り返り懐かしむことができるのは生きているからこそ──、そう結論付け、伊藤が自殺した屋上に亜弥とともに向かった主人公は、友の死によってぐらぐらと揺らいでいた自身のコップを強い意志を持って立て直します。
自殺という重いテーマに哲学的な要素を絡めた話であったため、読んでいて少し陰鬱な気分になるところもありましたが、普段考えないことを想像するきっかけにもなり、その点では意義深い内容だったと思います。
追伸
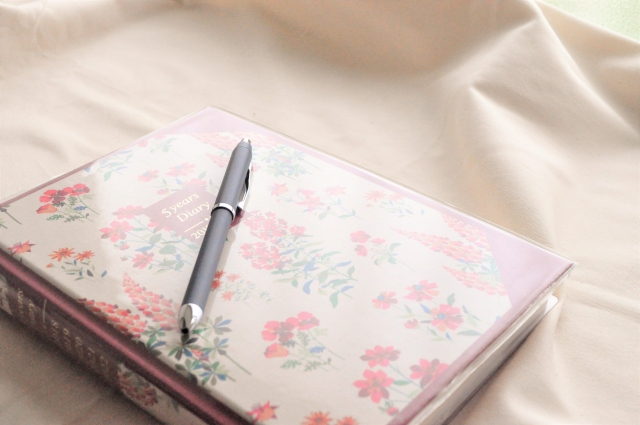
■あらすじ
小学一年のときに母親ががんで亡くなり、伯母から一冊のノートを渡された少年。それは母が書いた闘病日記で、そこには、ガンに冒された母の本音が克明に綴られていました。ときには弱音を吐くような苦しみの言葉で、またときには気丈に病と向き合おうとする明るい文体で――。
それから数日後、一人の女性(新しい母親のハルさん)が家にやって来ます。少年はその女性・ハルさんを、今までに一度も「お母さん」と呼んだことがなく、大人になっても彼女に対して心を開けないままでいました。
ある時、仕事でエッセイの執筆を依頼された僕(=大人になった少年)は、作品の中に虚構の存在として母親を登場させようとします。すると、読者から「母親にリアリティがない」と批判の声があがって――。
ドラマの題材によくなる、再婚後の義理の母親と子どものぎくしゃくした関係が描かれた最後の物語「追伸」。
作中で主人公は「自分にとっての母はたった一人だけだ」と言って義理の母親を拒み、決して「お母ちゃん」と呼ぶことはありませんでした。
そうやって不和を広げ、修復不可能になるまで引き裂かれてしまった2人を見ていると、親子として理解し合うことはもう無理なのだろうかと、絶望視してしまうところがありました。
しかしそんな2人も、物語の最後で互いに心から向き合えることになります。
きっかけとなったのが、妻が口にした「新しいお母さんに懐かない息子を見て、あなたの母親ならどうすると思う?」の一言で、それによって主人公は、亡くなった母親の気持ちをすべて理解しているつもりで、実際は何も分かっていなかったのだということに気付かされます。
亡き母親から卒業し、新たな母を受け入れて初めて「お母ちゃん」と呼ぶ最後のシーンは、物語の締めくくりにふさわしい感動的な結びだったと思います。
本の作者「重松清」の紹介

重松清(しげまつきよし)
はこんな人だよ!
重松清さんは昔から大好きな作家の一人で、特に少年少女を主人公にした作品(「きよしこ」「くちぶえ番長」など)が大のお気に入りです。
彼の作品には、人の複雑な感情を繊細に描いたものが多く、傷ついたり・悩んだり・立ち直ったりと、ありのままの姿を見せる登場人物たちの存在にも魅力があります。
ちなみに、作品の一部は学校の教科書にも採用されていて、「卒業ホームラン」「カレーライス」などは小学校の国語の授業でも習います。
また、映像化作品もあって、最近で言うと、2017年にドラマ化された「ブランケット・キャット」や、2018年に映画化された「泣くな赤鬼(短編小説「せんせい。」より)」などが有名です。
感受性の高い「少年少女」はもちろん、傷つきやすい「大人」もつい涙してしまうような感動作ぞろいの重松清文学。
興味を持たれた方は、他の作品も読んでみてはいかがでしょうか。
▼重松清のおすすめ作品はこちら▼
■重松清のおすすめ短編作品一覧|感動し泣ける名作7選(直木賞受賞作含む)
▼重松 清(しげまつきよし)▼
■人物・略歴
1963(昭和38)年、岡山県久米郡久米町生まれ。中学・高校時代は山口県で過ごし、18歳で上京、早稲田大学教育学部を卒業後、出版社勤務を経て執筆活動に入る。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表する。
■受賞歴
・1991年
『ビフォア・ラン』でデビュー。
・1999年
『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。
・2001年
『ビタミンF』で直木賞受賞。
・2010年
『十字架』で吉川英治文学賞受賞。
・2014年
『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。
■主な作品
『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。

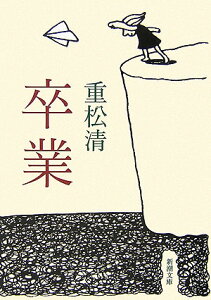


コメント