
こんにちは、
りんとちゃーです。
夏の新潮文庫100冊の「少年少女につづる本――」という紹介文に興味を惹かれて、ついつい衝動買いをしてしまった重松清の短編小説「きみの町で」。
この本は簡単に言うと、多様な登場人物(主に子ども)をまじえながら、正解のない哲学問題にせまる実験小説です。
短編小説の中でもとりわけページ数が少なく、一つひとつのエピソードも短めなので、普段本を読まない子どもに特におすすめです。
記事では、以下のことをまとめています。
■本の内容紹介と収録作品
■収録作品全11編の簡単なあらすじと感想
■著者「重松清」の紹介・プロフィール
夏休みの読書感想文の参考などにお役立てください。
本の内容紹介と収録作品
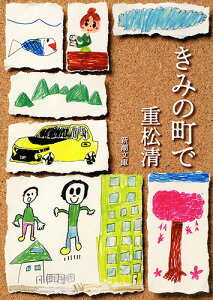
【Amazon.co.jp】きみの町で/重松 清 (新潮文庫)![]()
大切な友だちや家族を、突然失ってしまったきみ。人を好きになる、という初めての気持ちに、とまどっているきみ。「仲良しグループ」の陰口におびえてしまうきみ。「面白い奴」を演じていて、ほんとうの自分がわからなくなったきみ――。正解のない問いや、うまくいかないことにぶつかり、悩むときもある。でも、生きることを好きでいてほしい。作家が少年少女のためにつづった小さな物語集。
(新潮文庫「きみの町で」内容紹介より)
この短編集には、以下の11編が収録されています。
■収録作品
・電車は走る
・好き嫌い
・ぼくは知っている
・あの町で春
・あの町で夏
・あの町で秋
・あの町で冬
・誰かとウチらとみんなとわたし
・ある町に、とても……
・のちに作家になったSのお話
・その日、ぼくが考えたこと
以下は、それぞれのエピソードのあらすじと感想のまとめになります。
あらすじと感想
電車は走る

――よいこととわるいことって、なに?
それぞれの事情から、お年寄りになかなか席を譲れない子どもたち。
「二人のおばあさんの一人だけに席を譲るのは逆に良くないのでは?」と悩むカズオ、「席に座っている人にもその権利がある」と主張するタケシ、「いつもなら譲るけど体調がわるくて今日は・・」と申し訳なさげなヒナコ、勇気を出して席を譲ったのに、まわりから冷たい目を向けられて「どうして?」と苛立つサユリ。
席を譲らないのはわるいこと――。そう子どもの頃に教わりますが、世の中には色んな事情を抱えている人がいて、そういうことを考慮せずに、ただ単純にわるいと決めかかるのはよくないことです。
人の数だけ正しさがあり、必ずしも自分の正しさが他人の正しさと一致するとは限りません。大多数の正しさ(常識)からはみ出してしまう正しさもあるでしょう。
よいこと・わるいことは明確に決められず、その境が実は曖昧であることに気付かされるお話でした。
好き嫌い
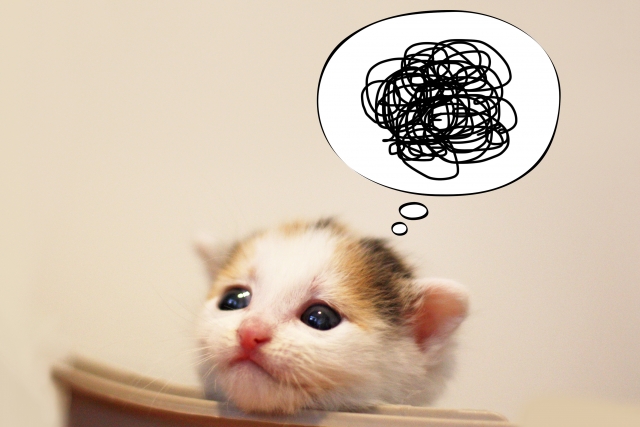
――きもちって、なに?
好きや嫌いといった『気持ち』について考えるヤスハル。
(大好きなサユリちゃんが他の男子といると気分が悪くなるけど、この気持ちはいったい何なのだろう――。)
好きや嫌いの『きもち』は理屈では説明できません。嫌いなのに好きってこともあるし、好きだけど嫌いってこともあります。
そしてそんな『きもち』に人は簡単に振り回されてしまいます。
分かっているようでいて実はよく分かっていない『きもち』。
あらためてその不思議さを考えさせられました。
僕は知っている

――知るって、なに?
(ボクは何でも知っている。人より物知りで勉強に関する知識なら負けない。そんなボクでもカワムラさんのことは分からない。
あと、クラスメイトのスドウがいじめられているのも知っている。いじめがだめなことも知ってるけど、いじめる側の気持ちが分かるから何もできなくて・・。)
人は物を知りすぎると臆病になります。頭がいい人ほどずる賢く打算的になり、心のおもむくままに行動できません。
知識は生きる知恵になるとか、世渡りのために役立つとかよく言いますが、本来は『誰かのため』
物事を知ることで、相手をより理解でき役に立つことができる――、そういった動機をもとにした学びを心がけたいものです。
あの町で 春

前3編の子ども哲学とはうって変わり、ここからは震災の話が描かれます。
未曾有の厄災に見舞われながらも、屈託なく咲く桜の花。
作中に登場する「振袖山(ふりそでやま)」はそんな桜が一夜にして散ってしまった伝説のある山です。
山の名前の由来となったのは古語の「袖振る」で、以下の2つの意味のうちの、後者(②)に語源があると言われています。
①大切な人と別れたり送り出したりする際に、服の袖を振って惜別の思いや愛情を示すこと
②死者の魂をこの世界に引き寄せ招き入れること
つまり袖振山とは、亡くなった人に出会える場所なのです。
厄災で家族を失った少年は、それを知ってか知らずか毎日のように山を登ります。
そして、頂上から海に向かって「おーい」と呼び掛けます。それは、亡くなった親や兄弟に向けられたものでした。
その後、少年は親戚に引き取られて街を出ることになり、最後の日の夜、再び山を登って「おーい」と呼び掛けると、桜の花びらが渦を巻いて舞い上がり、まるで彼と共鳴するかのように息を合わせます。
翌日、姿が見えなくなった少年――。
街を出ていったのか、それとも亡くなった家族のいる海へと桜とともに旅立ってしまったのか、それは誰にも分かりません。
語り継がれる物語には伝えたいメッセージがあります。少年のような残酷な運命を子どもたちに経験させないこと、そして、悲劇を二度と起こさないために私たちに何ができるのか考えること、本作にはそんな訓示が込められているように感じました。
あの町で 夏

小学校の卒業式の前日に、グラウンドで野球をする子どもたち。
その中で投手を務める主人公の少年は、今度こそ相手チームの永遠のライバル・大介との決着をつけてやる、と意気込みます。
ところが、辺りが暗くなったため試合は中断。続きは明日の卒業式の後に行うことになります。
「じゃあ、また明日」と手を振って彼と別れた翌日、突然起きた厄災によって2人は永遠に会えなくなって──。
先の未来に何が起こるかなんて分かりません。もしかしたら大切な人がいなくなるかも知れないし、自分がこの世を去るかも知れません。
一日一日を無為に過ごすのではなく、あとで悔いないように、日々最良の選択をとる――、そういうことを常に心がけたいものです。
あの町で 秋

娘と一緒に川べりを歩いていて、鮭が川をのぼってきたことに気付く父親。
鮭には、川で生まれて海で育ち、また川に戻る習性があります(=遡上)。しかしそんな鮭でも、この春に起きた厄災のことは知るよしもありません。
父親には悩みがあり、「震災で行方不明になった母親はもう帰ってこない」と娘に伝えれないでいました。それは、どうしても心の中で「もしかしたら・・」と淡い期待を感じてしまうからです。
川に帰るとすぐに死んでしまう鮭は、産卵して新たな生命を育むことで、命のバトンを繋いでいきます。
そんな鮭の姿を眺めながら、父親は「死という悲しい出来事を受けても、それを乗り越えて気丈に生きなければならない」と強く決意し、勇気を振り絞って娘に現実を伝えます。
鮭の川のぼりのエピソードとともに描かれた父と娘の再出発の物語。哀しくも美しい、そんな趣き深い内容だったと思います。
あの町で 冬

松の防風林、イチゴのビニルハウス、瀟洒(しょうしゃ)な住宅・・。そんな海岸にあったいつもの街並みが、地震の津波で一変します。
変わり果てた街に、瓦礫(がれき)処理のアルバイトでやって来た少年。
現地で少年は、先輩にこんな話を聞きます。
雁風呂(がんぶろ)──。
雁は、海を渡ってくる時に枝を加えてやって来る。その枝は休むときの「止まり木」にするためのもので、使い終わったら海岸に落とし、また北へ帰るときに加えて持っていく。しかし、死んでしまった雁は枝を持っていくことができず、海岸には枝だけがとり残される。
昔の人は、雁の遺品の枝を雁風呂にして焚きあげ、その命を弔っていました。
被災地の瓦礫も雁の枝のようなもので、本来なら機械的に処理せずに、きちんと供養すべきなのでしょう。ただ、あまりにも数が多いため、そういったことができないでいる現実があります。
少年は祖母が亡くなった時にそれを身をもって体験していて、だからこそ被災地の瓦礫処理の仕事に自ら志願したのでしょう。
震災の話の最後にふさわしい、被災者への哀悼の意を感じるストーリーでした。
誰かとウチらとみんなとわたし

――いっしょに生きるって、なに?
「風邪をひいて声が出なくなった私。でも学校を休むわけにはいかない。なぜって?カゲグチの標的になるのが嫌だから――。」
仲良しグループのみんなと話を合わせて、輪から外れないようにと気をつかいながら、「外れたら標的にされるかも?」と不安を抱く少女。
そんなグループの関係は、本当に『仲良し』と言えるのでしょうか・・。
日本は『和』を重んじる国で、周りと協調したり空気を読むことが美徳とされています。
でも人は、他人と違っているのが本来の姿であり、無理に相手に合わせて気を遣うと、息苦しくなって、いつかは心を病んでしまいます。
協調性はもちろん大事です。社会生活をおくる上で、空気を読まないことはトラブルのもとになります。でも、だからと言ってそればかりを気にしていたら、個性やその人らしさが稀薄になってしまいます。要は両者のバランスが大切なのでしょう。
ある町に、とても・・
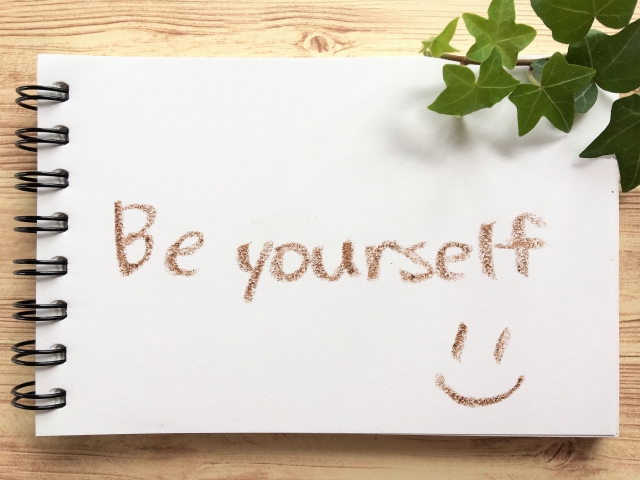
──自分って、なに?
「ある町にとても子ども思いの◯◯がいた」の冒頭で始まる、異なる人物の視点で描かれたショートストーリー。
「人生は他人との勝負じゃないから、自分らしく頑張れ」と息子にアドバイスする父親――。
でも息子は、頑張らないでぼーっとするのが好きで、「そっちのほうが自分らしいのに、頑張らないといけないのは変じゃない?」と不満を口にします。
娘が大人になったときに振り返れるよう、イベントがある度にビデオカメラで撮影する母親――。
それに対し娘は、「映っているのは自分ばかりで、周りの人が映っていない」と文句を言います。
人を笑わせるのが上手く、クラスで人気者の少年――。
でも彼は、本当は根暗な性格で、ただ人から好かれるように演じているだけで、「そんな自分は本当の自分じゃないのでは?」と悩み始めます。
相手のことを思って親切心でしたことが、結局は価値観の押しつけになってしまった前半2つの話。
自分らしさとは何か?、仮面を被った姿も含めて自分と言えるのか?、そういった自分らしさの定義について悩む3つ目の話。
短いストーリーの中に哲学要素がぎゅっと詰まった、そんな意義深い内容だったと思います。
のちに作家になったSの話

――自由って、なに?
これまでの話が、書籍『子ども哲学』の付録として書かれたものであると作者によってネタばらしがされます。
そして、最後から2番目の物語として、自由・不自由とは何かを考える作家S(おそらく重松清自身)の話が語られます。
親友の突然の訃報を聞いたSは、自分が何もできなかったことをひどく悔やみます。
自由を基盤とする社会において、自ら命を断つ「自由」は当然のごとく存在しますが、Sはどうしてもそれが納得いきませんでした。
人間は不自由な生き物で、食事や睡眠をとらないと生きていけません。また、社会を生きる上で、窮屈さや息苦しさを感じることが往々にしてあります。
そんな不自由な境遇でありながらも、それに負けじと頑張るところにこそ、楽しみや喜び(=自由)があるではないでしょうか。
死を選ぶことそのものは否定せず、ただ不自由から解放されるために自由へ逃れる(=死を選ぶ)という悲しい選択だけはしてほしくないと願う、そんな著者の思いを感じる物語でした。
その日、ぼくが考えたこと

――人生って、なに?
テレビのニュースで小学五年生の男の子が交通事故にあったと報道され、それを見た少年は、自分が今家族とともに何事もなく暮らしていることがとても幸せなんだと感じます。
次にニュースで流れてきたのは、飢餓で苦しむアフリカの少女の映像で、その時に少年は、日本で生まれたことは幸せなんだと感じる一方で、こんなことも考えます。
(本当に自分は幸せなのだろうか──。)
事故にあった小学生は、もしかしたら短くても幸せな人生を送っていたのかも知れなし、アフリカの少女も、いつもは笑っていたのかも知れません。
幸せは絶対的に存在するものではありません。どんなにつらい境遇でも、その人の心の持ち方次第で幸せに生きることができます。
逆に、恵まれた環境であっても、心ひとつで幸せを感じれなくなることもあります。まさに、相田みつをの言葉「しあわせはいつもじぶんのこころがきめる」そのものです。
幸せは得るものではなく、そこにあるもの――。それに気付かないと、満たされない幸福をずっと追い求め続けることになります。
小説の最後にふさわしい、幸せとは何かについて考えさせられる、読後感の良いエピソードでした。
著者「重松清」の紹介

重松清(しげまつきよし)
はこんな人だよ!
重松清さんは昔から大好きな作家の一人で、特に少年少女を主人公にした作品(「きよしこ」「くちぶえ番長」など)がお気に入りです。
彼の作品には、人の複雑な感情を繊細に描いたものが多く、傷ついたり・悩んだり・立ち直ったりと、ありのままの姿を見せる登場人物たちの存在も魅力になっています。
ちなみに、作品の一部は学校の教科書に採用されていて、「卒業ホームラン」「カレーライス」などは、小学校の国語の授業でも習います。
また、映像化作品もあって、最近でいうと、2017年にドラマ化された「ブランケット・キャット」や、2018年に映画化された「泣くな赤鬼(短編小説「せんせい。」より)」などが有名です。
感受性の高い「少年少女」はもちろん、傷つきやすい「大人」もつい涙してしまうような感動作ぞろいの重松清文学。
興味を持たれた方は、気になる作品を読んでみてはいかがでしょうか。
▼重松清のおすすめ作品はこちら▼
■重松清のおすすめ短編作品一覧|感動し泣ける名作7選(直木賞受賞作含む)
▼重松 清(しげまつきよし)▼
■人物・略歴
1963(昭和38)年、岡山県久米郡久米町生まれ。中学・高校時代は山口県で過ごし、18歳で上京、早稲田大学教育学部を卒業後、出版社勤務を経て執筆活動に入る。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表する。
■受賞歴
・1991年
『ビフォア・ラン』でデビュー。
・1999年
『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。
・2001年
『ビタミンF』で直木賞受賞。
・2010年
『十字架』で吉川英治文学賞受賞。
・2014年
『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。
■主な作品
『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。



コメント