
こんにちは、
りんとちゃーです。
小説「また次の春へ」(文春文庫)は、東日本大震災をモチーフにした連作短編集で、被災者・家族・支援者それぞれの視点から見た震災のリアルが描かれています。
憤りを覚える人や、やりきれなさを感じる人、必死に立ち向かおうとする人など、悲劇的な厄災に対する人々の思いはさまざまです。
記事では以下のことをまとめております。
■本の内容紹介と収録作品
■収録作品7編のあらすじと感想
■著者「重松清」の紹介・プロフィール
物語の大まかなあらすじの把握並びに、内容のおさらいとしてお役立てください。
内容紹介と収録作品

【Amazon.co.jp】また次の春へ/重松 清 (文春文庫)![]()
小学3年生、母を亡くした夜に父がつくってくれた”わが家” のトン汁を、避難所の炊き出しでつくった僕。東京でもどかしい思いを抱え、2カ月後に縁のあった被災地を訪れた主婦マチ子さん。あの日に同級生を喪った高校1年生の早苗さん…。厄災で断ち切られたもの。それでもまた巡り来るもの―。未曽有の被害をもたらした大震災を巡り、それぞれの位置から、再生への光と家族を描いた短篇集。
―――文春文庫「また次の春へ」内容紹介より
この短編集には以下の7編が収録されています。
■収録作品
・トン汁
・おまじない
・しおり
・記念日
・帰郷
・五百羅漢
・また次の春へ
以下は本編のあらすじと感想まとめになります。
あらすじと感想
トン汁

■あらすじ
母が突然の病気で他界し、兄弟3人と父親で新たな生活を送ることになった家族。葬儀か終わり、母がいなくなった居間で家族4人が座っていると、突然、父が「何か食べるか?」と言い出します。
どうやら、みんなのために「トン汁」を作ってくれるそうで、出来上がったその料理は、もやし入りのオリジナルで、体がとても温まるものでした。でも、お世辞にも味は良いと言えるものではなく・・。
家族にとっての特別な料理となった「トン汁」にまつわる最初のお話です。
どんな家族にも、その家庭ならではのオリジナルのメニュー・味があります。物語の登場人物たちが「トン汁」に唐辛子や卵を入れたように、料理には特別な想いが込められるものです。皆さんの家庭では「トン汁」に何を入れていますか?
思い出の味が懐かしくなってお腹が空いてくる、そんな不思議なストーリーでした。
おまじない

■あらすじ
東京のマンションで、体験したことのない揺れの地震を経験したマチコ。テレビをつけると津波警報が発令されていて、警報区域の中に小学生時代に暮らした町の名前がありました。それを見てマチコは「被災した町のために自分は何もしないでいいのか・・?」と落ち着かない気分になり、町に行くことを決意します。
その後、休みをとって町を訪れたマチコ。かつて遊んだ公園を見つけ、当時を思い出しながらブランコに近づいていくと、小学生たちが身に覚えのある合図をしてブランコをこいでいるのに気付きます。それは自分が子どもの時に作った『おまじない』で――。
小学生の一時期を過ごしただけだから・・と、町に来ても自分がよそ者に思えて仕方がなかったマチコでしたが、子どもたちの「おまじない」を目にすることで、私はここに存在していたんだと強く実感することになります。
「おまじない」を中心に展開する話は演出的に面白く、主人公をはじめとした被災地に関わる人の心情を美しく繊細に描いていたところも良かったと思います。
しおり
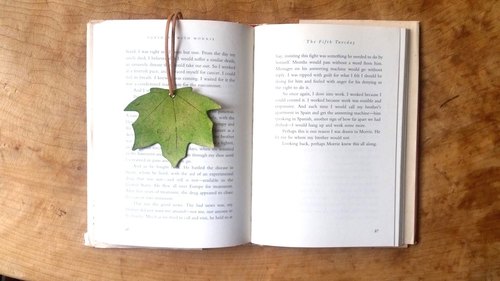
■あらすじ
高校の入学試験の最中に地震を経験した早苗。その時の揺れは大したことなく、試験後の帰り道に親友の慎也と試験内容の話をします。
時は過ぎ――、中学から高校へとバトンが渡った3月に、すべてを飲み込む厄災が街を襲い、不運にも慎也は津波に巻き込まれて行方不明になってしまいます。
運命のいたずらを憎く感じる早苗。しばらくして、慎也の母親の由美が「あなたから借りてたものみたい」と言って一冊の本を早苗のところに持ってきます。それは、試験の時に彼女が貸した本で、中には葉っぱの『しおり』が挟まれていました――。
津波による被災者には行方不明者が多く、遺体が見つからないからその死をなかなか受け入れられない、という人がたくさんいます。
亡くなったと分かれば心から悲しめるのに、わずかな希望が残されるがゆえに気持ちに踏ん切りがつけらない――、そんな被災者の気持ちを、この物語は『しおり』と『本』を交えて美しく描いています。
特に、作中のセリフ「また、明日――」で象徴される『小さな未来がやって来ること』の証となる『しおり』の存在が、切なくて印象的でした。
誰だって将来に大きな災いが起こるなんて思いもしません。しかし、来るべき未来が無慈悲に壊されるくらいに、現実というのは残酷なものです。
物語を読みながら、今私たちが何の問題もなく生きていることが幸せであること、さらに現実世界の理不尽さや割り切れなさに対して、時には踏ん切りをつけなければいけないこと、そういったことを考えさせられました。
記念日
 :
:
■あらすじ
「担任の先生の発案で、被災者にカレンダーを送ることになった」と母親に話す舞衣。しかし家に新しいカレンダーはなく、仕方なく今使っている家族の記念日の書き込まれたものを送ることになります。たださすがにこのままじゃまずいのでは・・と後で思えてきて、マークは全て消すことにしました。
その後、受け取った佐藤さんというおばあさんから「消していた部分に何が書き込まれていたのか教えてほしい」と連絡が入ります。それを聞き、家族を津波で失った彼女に申し訳なさを感じつつも、正直に記念日を教えることにした舞衣。
月日は流れ、8月の舞衣の誕生日に、見知らぬ相手から宅急便が届きます。それは、あの佐藤さんからの届け物で──。
誰かの記念日がまた別の誰かの記念日となる――。
震災で娘を失った佐藤さんにとって、舞衣たち家族は心の支えとなる存在で、そんな相手とカレンダーを通じてつながるストーリーは心あたたまるものがありました。
2つの家族の出会いによって作られた新しい『記念日』が、素敵な日になることを願うばかりです。
帰郷

■あらすじ
長年住んだふるさとに帰ってきたノブ。しかし、夏祭りを迎えたその村に、かつてのような活気はありませんでした。村の恒例行事の夏祭りには、毎年、都会に出た人が帰省して参加していましたが、今年は誰も帰ってこない状況で・・。
そのことにノブは先行きの不安を感じ、これからどうすべきだろうかと悩みます。そんな中、中学で習った三好達治の詩の一節を思い出したノブは、親友のコウジと一緒に寺のお堂を訪問し、そこでさまざまな願いが書かれた絵馬を見つけます、そして・・。
断ち切られた未来と現実味のない願いの数々──。
たとえいびつなかたちであっても、子どもたちの未来を切に願う親の気持ちに変わりはなく、そんな想いの端に触れることでノブは心を強く揺れ動かされます。
不幸な運命と理不尽な現実――。お堂でノブが見せた祈りは、はたして誰に向けられたものだったのでしょうか。ほのかな余韻を残す最後が印象的でした。
五百羅漢

■あらすじ
「同級生の山本が、卒業後に両親のいる地元に帰った際に震災に巻き込まれた」、その話を教え子の竹内くんから聞かされた私は、身内や知り合いに被災した者はいないものと決め込んでいたため、不意打ちを食らったような気分になります。
それから数日後、「五百羅漢(ごひゃくらかん)※1」がある故郷の寺を訪れた私は、そこで優しく包むような眼差しで佇むある像を見つけます。それは幼い頃に亡くなった母親とまったく同じ顔をした羅漢像で――。
(※1)五百羅漢・・別名「阿羅漢(あらかん)」。敬意を示すべき聖人がモチーフになった像。
大切な人が生きていた頃の姿を思い出させる遺品は、残された人にとって何より大事なものです。
息子の遺影となる写真を探す両親と、幼くして亡くした母の面影を探して五百羅漢を訪れる私の2つのエピソードは呼応するものがあり、「喪失による心の痛み」や「故人への偲び」という心情が鮮やかに描かれていたように思います。
また次の春へ

■あらすじ
震災の津波で父と母を失った洋之のもとに、ある日一通のダイレクトメールが届きます。宛先は両親で、差出人は何と北海道のM町の役場。訝しみながら洋之が封を開けると、そこには「メモリアル・ベンチ」と書かれていました。
その後、北海道のM町を訪れた洋之は、メモリアル・ベンチの担当だという星野さんに案内され、桜並木の並ぶ公園へとやってきます。すると星野さんが「この場所では鮭が遡上するんです」と声をかけてきます。どうやら両親も、その遡上の瞬間を見ていたらしく――。
鮭は川を登り、産卵してその命をまっとうします。そして春になると稚魚が川を下り、また大人になってふるさとの川に帰ってきて新たな命を繋ぎます。
一つの命の終わりと新たな命の始まり――。
病気で自分の命は長くないかも知れないと考えていた洋之にとって、鮭が遡上するその地はどう映ったのでしょうか。
命の尊さや儚さ、そして未来を信じ、新たな春がやって来ることを願って必死に生きようとする人々の姿を描いた短編作品「また次の春へ」。その結びにふさわしい、深い余韻をもたらすラストだったと思います。
著者「重松清」の紹介

重松清(しげまつきよし)
はこんな人だよ!
重松清さんは昔から大好きな作家の一人で、特に少年少女を主人公にした作品(「きよしこ」「くちぶえ番長」など)がお気に入りです。
彼の作品には、人の複雑な感情を繊細に描いたものが多く、傷ついたり・悩んだり・立ち直ったりと、ありのままの姿を見せる登場人物たちの存在も魅力になっています。
作品の一部は学校の教科書に採用されていて、「卒業ホームラン」「カレーライス」などは、小学校の国語の授業でも習います。
また、映像化作品もあって、最近でいうと、2017年にドラマ化された「ブランケット・キャット」や、2018年に映画化された「泣くな赤鬼(短編小説「せんせい。」より)」などが有名です。
感受性の高い「少年少女」はもちろん、傷つきやすい「大人」もつい涙してしまうような感動作ぞろいの重松清文学。
興味を持たれた方は、気になる作品を読んでみてはいかがでしょうか。
▼重松清のおすすめ短編作品はこちら▼
■重松清のおすすめ短編作品一覧|感動し泣ける名作7選(直木賞受賞作含む)
▼重松 清のプロフィール▼
■人物・略歴
1963(昭和38)年、岡山県久米郡久米町生まれ。中学・高校時代は山口県で過ごし、18歳で上京、早稲田大学教育学部を卒業後、出版社勤務を経て執筆活動に入る。現代の家族を描くことを大きなテーマとし、話題作を次々に発表する。
■受賞歴
・1991年
『ビフォア・ラン』でデビュー。
・1999年
『ナイフ』で坪田譲治文学賞、同年『エイジ』で山本周五郎賞を受賞。
・2001年
『ビタミンF』で直木賞受賞。
・2010年
『十字架』で吉川英治文学賞受賞。
・2014年
『ゼツメツ少年』で毎日出版文化賞を受賞。
■主な作品
『流星ワゴン』『疾走』『その日のまえに』『きみの友だち』『カシオペアの丘で』『青い鳥』『くちぶえ番長』『せんせい。』『とんび』『ステップ』『かあちゃん』『ポニーテール』『また次の春へ』『赤ヘル1975』『一人っ子同盟』『どんまい』『木曜日の子ども』など多数。


コメント